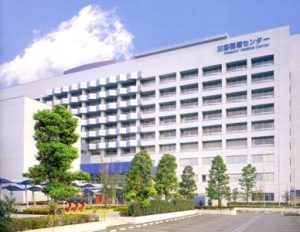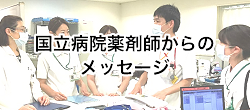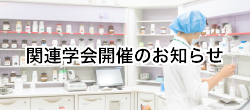関信地区国立病院薬剤師会 各施設の詳細は、こちらのページからご覧下さい。
| 感染制御認定薬剤師 |
| 徳島大学 2016年卒業 |
 |
| M . N |
| 埼玉病院 |
|
近年、感染防止対策加算に続いて、抗菌薬適正使用支援加算が制定された。さらに、2020年度診療報酬改定において、ASTの役割が拡充され、感染分野の重要性は増してきている。
当院では、特定抗菌薬(抗MRSA薬、カルバペネム系抗菌薬)の開始・長期使用の確認後と、菌血症患者でのグラム染色で主にGPC、GNR、酵母様真菌の検出を確認後に、医師へのフィードバックを全症例に対して行い、さらに同定時にはdefinitive therapyの提案を行っている。また、主治医より依頼のあった症例については、ICT、ASTと感染症専門医で定期的に協議を行っている。これにより感染症例のほぼ全例で不要な広域抗菌薬や不適切な抗菌薬を使用せず早期に治療されており、病院内での耐性菌防止にも貢献している。
また、新しい取り組みとして、薬剤師が感染症兆候のある患者にフィジカルアセスメントを行い、侵入門戸や感染巣もしくは非感染症の可能性について医師とともに検討している。そして、より効率的な治療の提供が可能となるよう微生物検査室と連携を行い、検査前、検査、検査後に介入する、diagnostic stewardshipを支援している。将来的には現状よりも更に感染症治療に食い込んでいき、患者と深く関わることがこれからの感染症薬剤師がすべき治療への貢献だと考えている。
学生に向けて
昨今の学生に、興味ある分野を尋ねると、口をそろえて「まだ、わからないです」と返ってくる。しかし、資格の取得や専門分野での業務を考慮すると、ある分野に興味を持つことは早いに越したことはない。理想の薬剤師像への近道は、まずは数多くの良い先輩を見ることだと考える。できれば様々な分野で尊敬する先輩の素敵なところを見つけて吸収してほしい。そうしているうちに、自ずとやりたいことは見えて来る。これからの薬剤師の必要性、存在意義について一緒に考え、盛り上げていきましょう。
|
ページトップへ戻る
| 精神科薬物療法認定薬剤師 |
城西大学 2005年卒業
北里大学大学院 修士課程 2007年修了 |
 |
| S . I |
| 小諸高原病院 |
|
私が勤務する小諸高原病院は、長野県東部にある340床の精神科と重症心身障害者の患者さんへ医療を提供している病院です。当院の薬剤科は薬剤師3名と助手1名の小規模施設です。主な業務は調剤業務と薬剤管理指導になりますが、採用薬品の選定から医薬品の適正使用の促進など、業務内容は多岐にわたります。精神科における薬剤管理指導では、治療の効果や副作用の判定をする客観的な数値がないものが多いことが特徴です。例えば、患者さんが日中の眠気を訴えたとしても「夜に眠れているのか」「日中にやることがなく、昼夜逆転した生活になっていないか」「夜間の頻尿はないか」など薬以外の原因や、薬が原因であったとしても、「眠気の出現時期と薬歴から考えて原因薬剤はあるか」「不眠時頓服薬を使用する時間が遅すぎないか」「薬物相互作用で眠気が強い薬が増強していないか」など仮説を立てて、患者さんや患者さんを観察する看護師やリハビリスタッフから聞き取った情報と薬歴を組み合わせての推測が必要になります。時には他職種に観察項目の追加をお願いする場合もあります。原因が異なれば対処方法も異なり、処方変更を伴わない解決策を提案することがあるのが、精神科の薬剤管理指導における醍醐味だと思います。
当院は医師も20名以下と全員顔見知りの職場で、コメディカルも同様です。そのため、医局や他部署にもいつでも気軽に相談に行くことが出来る風通しの良い職場です。炭酸リチウムを適正使用するために定期採血を強化したいと思えば、検査科に外来からの血中濃度測定依頼が月50件増えても対応可能かとすぐに相談に行き、医局会で医師全体に検査オーダー依頼をすることも出来ます。
私は精神科薬物療法認定を取得しましたが、これをベースに緩和医療に携わることを次の目標にしています。国立病院機構は転勤がありますが、広い領域を学びたい場合には就職先の候補にして頂ければと思います。
|
ページトップへ戻る
| 妊婦・授乳婦認定薬剤師 |
| 東北薬科大学 2007年卒業 |
 |
| N . S |
| 国立成育医療研究センター |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
調剤業務と薬剤管理指導業務、また周産期病棟の常駐薬剤師として業務しています。
患者さんのなかには妊娠・授乳期の薬剤使用に対する不安から服薬を我慢したり、自己判断で服薬を中止して基礎疾患を悪化させたりしてしまう方がいます。添付文書等の妊婦・授乳婦の項だけでは患者さんを納得させる説明が難しいため、現状に即した情報収集を行い医師と協議して説明することがあります。
2)職場の雰囲気は?
当院は小児と周産期の専門病院のため、複雑な散剤調剤や混注業務が多くあり、日々緊張感をもって調剤しています。薬剤部内では積極的に研究や学会発表に取り組んで切磋琢磨しています。病棟では常駐を始めてからより一層、医師や看護師から薬剤の相談を受ける機会が多くなりました。またカンファレンスでは多職種間で情報交換を行い、患者のより良い治療のために連携しています。
3)仕事のやりがいは?
薬物治療が必要な妊婦・授乳婦さんに適切な情報提供を行い患者さんに正しく理解してもらえた時にとてもやりがいを感じます。また、無事に赤ちゃんを出産された様子を見られた時には安堵と喜びがあります。
4)今後の目標や夢は?
妊娠期の薬剤使用の情報提供は難しいリスクコミュニケーションが求められるため、さらに技術を磨いていきたいと思います。また、妊婦・授乳婦薬物療法専門薬剤師を目指して未来の妊婦・授乳婦さんの役に立つ研究を考えたいです。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ
国立病院機構には幅広い分野を学べる総合病院から専門性の高い病院まで様々な施設があります。薬剤師としては一つ一つが貴重な経験になるのでそこから多くのことを学び、患者さんの治療に貢献できるスキルを身に付けていってください。
|
ページトップへ戻る
| HIV感染症薬物療法認定薬剤師 |
| 日本大学 2015年卒業 |
 |
| A . K |
| 国立国際医療研究センター病院 |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
当院には、薬害エイズ訴訟の和解を踏まえ、被害者救済の一環としてエイズ治療・研究開発センター(AIDS Clinical Center, ACC)が設置されています。国内外におけるHIV感染症の治療・研究機関と連携し、最先端の医療を提供するだけでなく、新たな診断や治療の開発のための臨床研究、基礎研究を行っています。
近年HIV感染症は、毎日の服薬が継続できればコントロールが可能な慢性疾患とも言われています。患者さんが安心して服薬を継続していけるよう、直接の服薬指導だけでなく、薬物間相互作用の確認、新薬を含む薬剤情報の提供、処方提案、薬物血中濃度の測定など幅広い薬学的介入を行っています。
ACCは全国の医療従事者に対する研修会の実施などを行っており、薬剤部としても全国の拠点病院や近隣の保険薬局と連携し、情報発信を積極的に行っています。
2)職場の雰囲気は?
HIV診療においては医師、看護師、薬剤師だけでなく、臨床心理士、社会福祉士、歯科衛生士など多職種で患者さんをサポートしています。お互いに信頼し合い、それぞれの専門性を生かして診療にあたっています。
3)仕事のやりがいは?
薬剤師としての情報提供や処方提案が治療方針に活かされ、患者さんが少しでも治療に前向きになってくれた時にやりがいを感じます。
4)今後の目標や夢は?
薬学的な知識・技能の向上だけでなく、患者さんの精神的・社会的支援の一端を担えるよう、日々の業務や研究発表などを通して精進していきたいと思っています。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ
病院薬剤師は、様々な医療従事者と関わることができ、多方面から患者さんをサポートすることの意義を実感することができます。また日常診療に加え、興味のある分野のスペシャリストを目指し新しいことに挑戦する多くの機会に恵まれています。ぜひ病院薬剤師に興味を持っていただき、視野の広い医療従事者になるために一緒に頑張りましょう。
|
ページトップへ戻る
| がん薬物療法認定薬剤師 |
| 明治薬科大学 2013年卒業 |
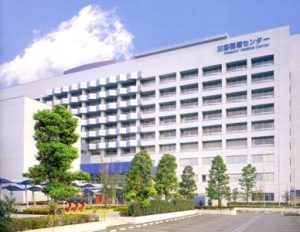 |
| R . N |
| 災害医療センター |
|
当院は名前の通り災害医療の中核を担う病院となっていますが、その傍らで地域がん診療連携拠点病院として地域のがん診療の中心としての役割も果たしています。その中で私はがん薬物療法認定薬剤師としてがんに関わる業務を主に担当しています。具体的には外来化学療法室における薬剤業務(服薬指導やレジメンチェック)、がん化学療法レジメンの管理業務(レジメン登録やその管理)、がん化学療法における院外薬局との連携(会議や研修会の開催)などです。がんに関連する業務以外にも病棟業務や調剤業務も常時行っています。
一般的に抗がん剤は通常の薬剤に比べて治療域が狭く副作用が出現し易いです。それを如何にして予防したり軽減したり出来るかが治療の質の向上につながります。患者さんの訴えや状態を把握し、それに対して薬学的アプローチで他職種の医療スタッフと協力して治療を安全かつ効果的に遂行していくことが求められます。それはがん以外の他の治療でも同じことが言えますが、がん治療はこのプロセスを経て患者さんや他職種の医療スタッフへの貢献をしっかりと実感できるところが魅力的だと思います。こうした実感が日々の仕事のやりがいとなっています。
医療現場は以前にも増して複雑化しておりチーム医療の重要性が色濃くなっています。それに比例して専門性を持ったスタッフが必要とされています。もちろん、薬剤師として幅広い知識を持つことは大切ですが、1つでも良いので興味のある分野や得意な分野をみつけて専門性を高めることを目指してみてください。そうすれば現場で必要とされる薬剤師へ一歩近づくことができると思います。私たちと一緒にチーム医療に貢献していきましょう。
|
ページトップへ戻る
| 緩和薬物療法認定薬剤師 |
| 明治薬科大学 2014年卒業 |
 |
| H . S |
| 渋川医療センター |
|
現在は調剤(処方・注射)や抗がん剤無菌調製、院内製剤等の中央業務をはじめ、呼吸器内科病棟や緩和ケア病棟における病棟業務、後輩や部員の育成等に取り組んでいます。その中で、緩和薬物療法認定薬剤師としては、主に緩和ケア病棟や緩和ケアチームでの医療用麻薬をはじめとした薬物の適正使用(薬剤選択・用量調整、薬物投与経路・剤形の変更、相互作用確認、効果・副作用確認、薬剤の追加・削除の提案等)や各病棟担当薬剤師と連携して緩和ケア医療に関わる薬物治療の充実化を図っています。緩和ケア医療については入職当初から興味があり、千葉医療センターの緩和ケアチームでは薬剤師1年目からチームの一員として参加させていただきました。チームで活動する中で、患者さんの病態や苦痛、不安を理解して、その解消により深く携わりたい、また、より専門的に緩和ケア医療に携わりたいと感じ、令和2年、緩和薬物療法認定薬剤師を取得しました。患者さんや家族とコミュニケーションを図る中で、医療用麻薬をはじめとした使用薬剤や苦痛に対する不安を取り除けたとき、また、医師、看護師等と協力して患者さんの状況を共有しながら上手く薬剤調整できたときは特にやりがいを感じています。
今後、緩和薬物療法認定薬剤師として、緩和ケア病棟や緩和ケアチームを始め、他の病棟を含めた病院全体、地域においてもより充実した緩和ケア医療、薬物治療をすることができるように医師や看護師、ソーシャルワーカー、栄養士等と協働していくこと、また、後輩薬剤師の育成にも努めていきたいと考えています。
国立病院機構では異動に伴い各施設での特徴を学ぶことができ、また、新しい施設で活かすことができます。まずは薬剤師として幅広い知識を身につけ、その上で緩和ケア医療に関するより専門的な知識を深めて、患者さんへの薬物治療に貢献できるよう一緒に働きましょう。
|
ページトップへ戻る
| 小児薬物療法認定薬剤師 |
| 明治薬科大学 2015年卒業 |
 |
| H . K |
| 埼玉病院 |
|
私は地域周産期母子医療センターを備えた地域医療の中核を担う総合病院で、調剤や病棟業務を行っています。
小児領域で使用される医薬品は、添付文書に小児に対する用法・用量が明確に記載されていないものが多く、適応外使用が全使用薬剤の70%を占めていると報告があります。より安全で有効的な薬物療法を支援するためには小児に対する適応の有無、用法・用量及び投与禁忌など、十分な注意が必要です。
病棟業務では前述のことを考えながら、小児薬物療法認定薬剤師としてできることはないか、日々考え、工夫しながら業務に取り組んでいます。小児への服薬指導と言っても、年齢により理解度やできることが異なるため、大人のようにすべて同じように説明はできません。例えば、炎症を火事と表現したり、抗菌薬と細菌を幼児向けの人気のキャラクターに例えて薬剤の説明をしたりします。また、年齢は同じでも、錠剤・カプセル・散剤を飲めるか、どんな味であれば飲めるかなど、考えることは様々です。
小児領域では本人だけでなく、キーパーソンとなる家族への説明も必要です。最近は共働きのご家庭が多いため、コンプライアンスを保てるように、退院後の生活をイメージして、服薬指導を行っています。また子供に薬を飲ませることを不安に思っている方は多くいます。薬に悪いイメージがあると薬の使用をやめてしまう方やインターネットに掲載されている間違った情報を持っているため、薬の使用を拒否する方もいます。そのような方へは何度も正しい情報を提供して、子供のために必要な薬だということを理解してもらいます。
子供にとって病院は楽しい場所ではありません。しかし医師、看護師、その他の医療従事者と協力して、子供が笑顔で入院できる医療現場を目指していきたいと思っています。
これから日本の将来を担う子供たちにより良い医療が提供できるように、ぜひ一緒に小児医療について勉強していきましょう。
私が緩和ケアに携わる中でやりがいを感じるのは、患者さんの苦痛が緩和されて笑顔が見られたときや、病を患いながらも一日一日を大切に過ごしている患者さんの人生に深く関わることができたときなどです。そういった気持ちを、一緒に悩みながら活動するチームメンバーと共有できるのも緩和ケアの魅力です。★国立病院機構には専門性の高い施設が沢山ありますが、様々な分野のジェネラルな知識の上にこそ専門性が成り立ちますので、これから薬剤師を目指す方には、幅広い視点を持って学んで頂けたらと思います。そして、がん診療に携わるすべての方が緩和ケアに関心を持ち、その中から志ある方が緩和ケアの普及や発展を目指して、一緒に活躍してくれることを願っています。
|
ページトップへ戻る
| NST専門療法士 |
| 帝京平成大学 2014年卒業 |
 |
| A . M |
| 千葉医療センター |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
当院は病床数410床、診療科37科(専門外来含む)の総合病院です。私は普段、調剤室・注射室業務、抗がん剤調整業務、病棟業務に加えて、NSTの一員としてチーム医療にも参加しています。NSTとは栄養サポートチーム(Nutrition Support Team)のことです。患者さんの栄養状態のアセスメント、適切な栄養ルートの検討、栄養剤・点滴内容の提案、勉強会の開催など、日々患者さんの栄養状態改善に向けた取り組みを行っています。NSTにおける薬剤師の役割は、TPNの処方設計や適切な栄養剤の選択支援、栄養剤と医薬品の相互作用の確認など多岐にわたります。私が取得しているNST専門療法士は、学会の定める学術集会、セミナーに参加して必要単位を取得し、40時間以上の実地研修を修了した後、認定試験に合格すると取得することができます。道のりはやや長いですが、セミナーや実地研修で得られた知識は調剤業務や病棟業務にも役立ちますので、興味があればぜひ挑戦していただきたいです。
2)職場の雰囲気は?
積極的に業務に取り組む職員が多いので、病院全体が活気に満ちています。
3)仕事のやりがいは?
服薬指導を通して患者さんが使用薬の内容を理解できるようになり、自己管理に自信をもって退院していく姿をみると嬉しくなります。また、NSTの介入後栄養状態が改善し、無事退院・転院された患者さんがいるとNSTの一員としてのやりがいを感じます。
4)今後の目標や夢は?
将来はNST専門療法士の上部資格である臨床栄養代謝領域専門療法士を取得し、得られた知識を基により細やかな栄養療法が提供できるようになりたいです。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ
当院をはじめ国立病院機構には、専門的な知識や資格・認定の取得を後押ししてくれる環境があります。就職後も医療人としてさらなる成長を続けたい方にはやりがいのある職場だと思います。意欲溢れる皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。
|
ページトップへ戻る
| 救急認定薬剤師 |
| 北里大学 2013年卒業 |
 |
| K . H |
| 東京医療センター |
|
1)普段はどのような仕事をしていますか?
普段は救命救急センターやICU(Intensive Care Unit:集中治療室)、CCU(Coronary Care Unit:冠動脈疾患を管理するICU)の病棟を担当しており、集中治療やICU管理が必要な患者の薬物療法に関わる仕事をしています。具体的には、処方内容・投与量の確認を行い、不適切な処方があれば医師へ照会しています。カンファレンスや病棟回診にも同行して、実際に投与されている注射薬の流速や投与ルートの管理、副作用マネジメントも行っています。また、TDM(Therapeutic Drug Monitoring:薬物血中濃度モニタリング)や患者個々の肝・腎機能に応じた投与量の調節などの処方提案・処方支援も積極的に実施しています。
2)職場の雰囲気は?
若手の職員が多く活気があり、上司も年齢が近く相談しやすい雰囲気です。認定・専門資格を持つ薬剤師が多く在籍しており、切磋琢磨できる環境です。
3)仕事のやりがいは?
救急・集中治療の領域は患者の命に深く関わる領域ですので、緊張感や責任感を強く感じますが、その分やりがいも強く感じます。
4)今後の目標や夢は?
今後の目標は救急認定薬剤師の資格を活かして、後進の指導・育成に尽力すると共に、救急・集中治療に関する知識の向上、今後新設される救急専門薬剤師の資格取得を目指していきたいと考えています。
5)薬剤師を目指す学生へのメッセージ
2016年度に病棟薬剤業務実施加算2が新設され、救急・集中治療領域に薬剤師を配置することで診療報酬がつき、薬剤師が医療チームの一員として活躍するようになるための環境が整えられた。また、2018年度には救命救急入院料のうち救急体制充実加算が改定され、この加算の施設基準において常勤薬剤師配置が評価項目として新たに追加されるなど、救急医療における薬剤師の評価が高まっています。今後救急専門薬剤師の資格が新設されることが決定しており、救急・集中治療領域は今一番注目されている領域です。
これから病院薬剤師を目指す皆様には、救急・集中治療の領域に興味を持ち、挑戦してくれることを期待しています。
|
ページトップへ戻る
| 褥瘡認定薬剤師 |
|
城西大学 2009年卒業
城西大学大学院 2011年卒業
|
 |
| M . A |
| 西新潟中央病院 |
|
褥瘡は骨突出部に持続的な圧迫が加わることでできる潰瘍であり、痛みを伴うことも多く患者のQOL低下の原因となることもあります。そのため、適切な治療を行い早期に治癒することが望まれます。褥瘡は個々の患者で発生要因や体格、環境などが異なるため多職種で協力して多角的に予防・治療にあたっています。
実際に業務で褥瘡治療に関わっているのは、月1回の褥瘡対策チーム会と病棟からの褥瘡治療薬の相談がメインとなります。褥瘡対策チーム会の症例検討会ではチームメンバーと創部写真を観察し、病棟の褥瘡患者では直接創部の確認を行い、薬剤提案や処置方法について医師や看護師とディスカッションをしています。
褥瘡治療薬は主薬の効果と軟膏基剤の特性の組み合わせで治療効果を示します。薬剤師として、褥瘡の早期治癒のため個々の患者の褥瘡に合わせた薬剤を処方提案できるように知識の取得と更新が必要となります。そのためには学会や研修会などに参加することが効果的です。多職種が集まるチーム医療で薬剤師の処方提案が受け入れられ、褥瘡が治癒に向かうことにやりがいを感じます。
現在は創面の状態に合わせた単剤を処方提案していますが、創面の水分量に合わせてより細かい調節ができるブレンド軟膏を使用した治療方法も報告されているため、今後はそのようなブレンド軟膏についても処方提案できるようになりたいと考えています。
大学ではあまり教わらない分野だと思いますが、褥瘡の分野でも薬剤師が活躍できるチャンスがありますので、興味を持って勉強してもらえたら嬉しいです。
|
ページトップへ戻る
関信地区国立病院薬剤師会 各施設の詳細は、こちらのページからご覧下さい。